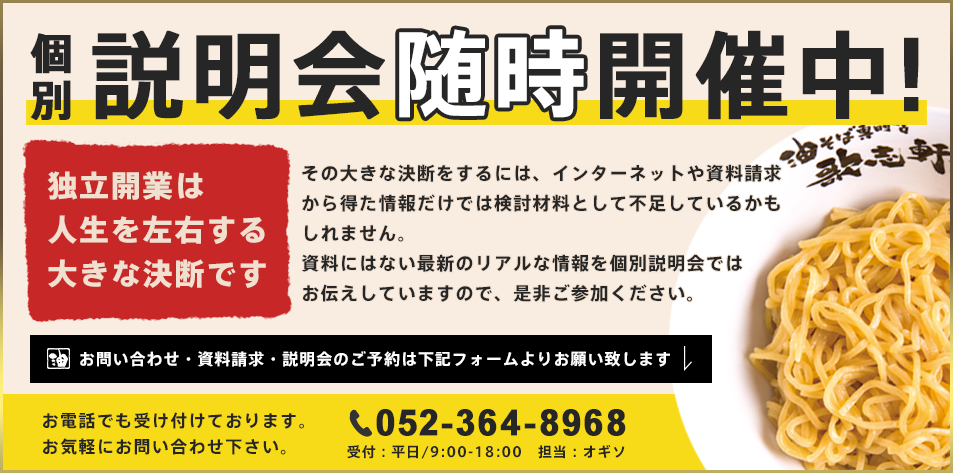ラーメンフランチャイズは儲かるのか?徹底解説

Contents
ラーメンフランチャイズが儲かる理由
売上の安定性

ラーメンフランチャイズが儲かる大きな理由の1つは、売上の安定性にあります。
独自のブランド力と知名度を持つフランチャイズチェーンに加盟することで、オープン時から一定の集客を見込むことができます。
これは、すでに多くの顧客から支持されている看板メニューやサービスを提供できるからです。
一方、個人店の場合は、認知度を高めるために時間と労力を要するため、売上が安定するまでには一定の期間が必要となります。
フランチャイズの場合、ブランドの信頼性と実績により、開業初日から安定した売上を期待できることが大きなメリットと言えるでしょう。
さらに、本部による集客支援やキャンペーンなども、売上の安定化に寄与します。
これにより、経営者は資金繰りに余裕を持つことができ、事業の継続性が高まります。
効率的な店舗オペレーション
ラーメンフランチャイズが儲かるもう1つの理由は、効率的な店舗オペレーションが可能な点です。
フランチャイズ本部は、長年の経験とノウハウをもとに、最適な調理工程や接客マニュアルを確立しています。
加盟店はこれらを導入することで、スムーズな店舗運営を実現できます。
具体的には、セントラルキッチンで仕込まれた食材を使用することで、店舗での調理工程を最小限に抑えられます。
これにより、人件費の削減と作業効率の向上が図れるのです。
また、POSシステムや在庫管理システムなど、本部が提供する各種ツールを活用することで、店舗運営に関わる事務作業の負担も軽減されます。
経営者は、販売促進や顧客満足度の向上など、より重要な業務に時間を割くことが可能となるでしょう。
原価管理のしやすさ

ラーメンフランチャイズが儲かる理由の3つ目は、原価管理のしやすさです。
フランチャイズ本部は、多店舗展開によるスケールメリットを活かし、食材や備品などを大量に仕入れることができます。
これにより、単価を抑えられるため、加盟店は安定した原価率を維持しやすくなります。
また、本部が集中購買を行うことで、加盟店側の発注業務も簡素化されます。
発注ミスや過剰在庫によるロスを防げるため、原価管理がより正確に行えるのです。
さらに、本部が提供するメニューは、原価率を考慮した上で設計されています。
加盟店は、提示された価格設定を守ることで、適正な利益率を確保することができます。
原価管理の難しさは、多くの飲食店経営者の悩みの種ですが、フランチャイズ方式なら、その課題をクリアしやすいと言えるでしょう。
最適化された店舗設計
ラーメンフランチャイズが儲かる理由の1つに、最適化された店舗設計が挙げられます。
フランチャイズ本部は、長年の経験とデータの蓄積をもとに、売上を最大化できる店舗レイアウトを設計しています。
厨房と客席の動線が最適化されているため、スタッフの作業効率が向上し、注文から提供までの時間が短縮されます。
これは、顧客満足度の向上につながり、リピート率の上昇が期待できるのです。
また、席数や客単価を考慮した店舗設計により、坪単価を最大限に引き出すことが可能となります。
無駄なスペースを排除し、限られた面積で最大の収益を上げられる店舗設計は、ラーメンフランチャイズならではの強みと言えるでしょう。
経営者の精神的余裕

ラーメンフランチャイズに加盟することで、経営者は精神的な余裕を得られます。
独立開業の場合、メニュー開発や仕入れ先の選定など、すべての業務を一から行う必要があります。
一方、フランチャイズ加盟店は、本部が提供する確立されたビジネスモデルに従うだけで、店舗運営が可能です。
これにより、経営者は本来注力すべき業務に集中できるのです。
また、フランチャイズ本部によるサポート体制も、経営者の精神的な支えとなります。
店舗運営に関する疑問や悩みを相談できる相手がいるという安心感は、大きな心の支えになるでしょう。
経営者が精神的に安定していることは、スタッフのモチベーション維持にも好影響を与えます。
結果として、店舗全体のパフォーマンス向上につながると考えられます。
加盟店同士の情報交換

ラーメンフランチャイズでは、加盟店同士の情報交換が活発に行われています。
本部主催の研修会や勉強会では、他店の成功事例や課題への対処法など、様々なノウハウを共有することができます。
また、加盟店オーナー同士の交流会では、日頃の悩みを相談し合ったり、アイデアを出し合ったりと、貴重な情報交換の場となっています。
こうした情報交換を通じて、自店の課題解決につながるヒントを得られることも少なくありません。
さらに、他店の取り組みを参考にすることで、自店の売上アップや経費削減など、具体的な成果につなげることも可能です。
加盟店同士が切磋琢磨し合える環境は、ラーメンフランチャイズならではの魅力と言えるでしょう。
失敗リスクの低減
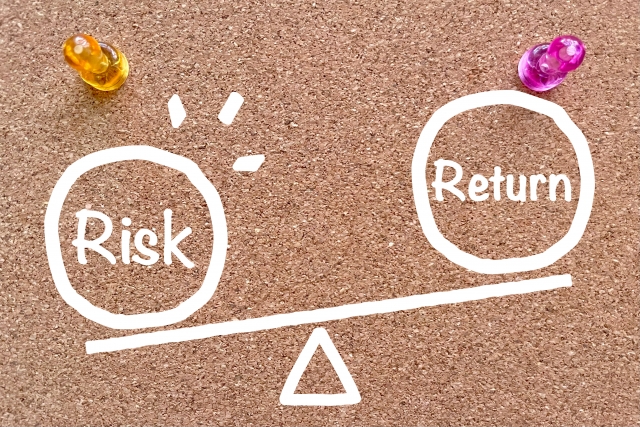
ラーメンフランチャイズに加盟することで、独立開業に比べて失敗のリスクを大幅に低減できます。
フランチャイズ本部は、長年の経験とノウハウをもとに、成功への道筋を明確に示してくれます。
加盟店は、本部が提供するマニュアルや教育システムに従うことで、安定した店舗運営が可能となるのです。
また、店舗物件の選定や設計、メニュー開発など、独立開業では時間と労力を要する業務も、本部がサポートしてくれます。
これにより、オープンまでのプロセスがスムーズに進むため、開業までの期間を短縮できます。
さらに、ブランドの知名度を活かした集客力も、失敗リスクを下げる要因の1つです。
加盟店は、初日から一定の来客数を見込めるため、安定した売上を確保しやすくなります。
こうした点から、ラーメンフランチャイズへの加盟は、失敗リスクを最小限に抑えながら、飲食店経営に挑戦できる方法と言えるでしょう。
ラーメンフランチャイズのビジネスモデル
加盟店経営者の平均年収

ラーメンフランチャイズ加盟店の経営者の平均年収は、店舗の規模や立地、売上によって大きく異なります。
一般的に、ラーメン店1店舗で年商3,000万円から4,000万円程度の売上があれば、経営者の年収は500万円から800万円程度になると言われています。
ただし、これはあくまでも平均的な数値であり、売上が伸びれば年収1,000万円以上も可能です。
一方で、立地や経営状況によっては、年収300万円程度にとどまるケースもあるようです。
ラーメンフランチャイズ加盟店の経営者の年収は、店舗運営能力や経営努力によって大きく左右されると言えるでしょう。
利益を最大化するための工夫と、継続的な改善が求められます。
加盟料とロイヤリティの仕組み

ラーメンフランチャイズに加盟する際には、加盟金やロイヤリティなどの費用が発生します。
これらは、ブランドの使用権や運営ノウハウの提供に対する対価として、本部に支払う必要があります。
加盟料とロイヤリティの仕組みは、フランチャイズチェーンごとに異なりますが、一般的な相場や計算方法について見ていきましょう。
加盟金の相場
ラーメンフランチャイズの加盟金は、チェーンによって大きく異なります。
比較的参入しやすいチェーンでは、100万円から300万円程度の加盟金で加盟できる場合もあります。
一方、知名度の高い大手チェーンになると、加盟金は1,000万円を超えるケースもあるようです。
加盟金は、店舗の設備や什器、看板などの初期費用に充てられることが一般的です。
加盟を検討する際は、加盟金の金額だけでなく、その内訳についても確認しておくことが重要です。
保証金について

加盟金とは別に、保証金の支払いが必要なチェーンもあります。
保証金は、契約が終了した際に返還されるものですが、契約期間中は本部が管理します。
保証金の金額は、チェーンによって異なりますが、数十万円から数百万円程度が一般的です。
保証金は、契約の履行を担保するための預り金としての性格があります。
加盟店が契約を守らない場合、保証金から違約金が差し引かれることがあるので注意が必要です。
ロイヤリティ料の計算方法

ロイヤリティは、加盟店が本部に対して支払う継続的な使用料です。
ブランドの使用権や運営ノウハウ、食材の供給などに対する対価として、売上の一定割合を支払うのが一般的です。
ラーメンフランチャイズのロイヤリティ料は、売上の3%から7%程度が相場だと言われています。
例えば、月商1,000万円の店舗で、ロイヤリティ料が売上の5%だった場合、毎月50万円を本部に支払うことになります。
ロイヤリティ料は、加盟店の売上に大きく影響するため、加盟前に料率と計算方法を十分に確認しておくことが大切です。
このレスポンスに追加されたユーザー例を参照しました。
事業理念と契約条件の確認
ラーメンフランチャイズへの加盟を検討する際、本部の事業理念や契約条件を十分に確認することが重要です。
フランチャイズチェーンごとに、経営方針や支援体制、ノウハウの提供範囲などが異なるため、自身の目指す方向性と合致するかを見極める必要があります。
特に、契約書の内容は詳細に確認しましょう。
ロイヤリティや広告費の負担割合、契約期間、売上目標、競業禁止条項など、加盟店に求められる義務や制限事項が明記されています。
これらの条件が自身の事業計画と齟齬をきたさないか、慎重に検討することが求められます。
また、本部の経営理念や企業文化を理解することも大切です。
長期的なパートナーシップを築くためには、双方の価値観が合致している必要があります。
本部の考え方に共感できるか、直接コミュニケーションを取って確かめておくことをおすすめします。
綿密な事業計画の作成

ラーメンフランチャイズへの加盟を決めたら、綿密な事業計画を作成しましょう。
事業計画は、資金調達や店舗運営の指針となる重要なツールです。
まず、売上予測と損益分岐点の算出が必要です。
想定される客単価や1日の来客数、ランニングコストなどを細かく積算し、どの程度の売上が必要か割り出します。
次に、初期投資の資金計画を立てます。
加盟金や内装工事費、厨房機器の購入費など、開業までに必要な資金を詳細にリストアップし、調達方法を検討します。
また、人件費や食材費、光熱費など、運転資金の予測も欠かせません。
資金繰りに余裕を持てるよう、少なくとも3ヶ月分の運転資金は確保しておくことが望ましいでしょう。
事業計画の作成に当たっては、本部のアドバイスを積極的に求めることをおすすめします。
経験豊富な本部スタッフが、売上予測や資金計画の作成をサポートしてくれる場合があります。
綿密な事業計画は、ラーメンフランチャイズ加盟後の安定した運営に直結します。
時間をかけて入念に作成することが、成功への第一歩となるでしょう。
テリトリー制度の確認
ラーメンフランチャイズへの加盟を検討する際は、テリトリー制度の有無とその内容を確認することが重要です。
テリトリー制度とは、加盟店の出店可能エリアを限定し、一定の営業保護を提供する仕組みのことです。
この制度があることで、近隣での過当競争を防ぎ、加盟店同士のバッティングを回避することができます。
ただし、チェーンによってテリトリーの範囲や条件は異なります。
例えば、半径500mを独占エリアとするケースや、人口10万人当たり1店舗までといった制限を設けているチェーンもあります。
加盟を検討する際は、自店の商圏が適切に保護されるか、本部に確認しておく必要があるでしょう。
メニューの自由度

ラーメンフランチャイズでは、本部が定めた標準メニューを提供することが基本です。
これにより、チェーン全体での味の統一性を保ち、ブランドイメージの維持を図っています。
ただし、メニューの自由度については、チェーンごとに方針が異なります。
一部のチェーンでは、加盟店独自のメニュー開発を認めているケースもあります。
地域の嗜好に合わせた限定メニューを提供できれば、差別化につながる可能性があります。
一方、独自メニューが認められないチェーンもあるため、加盟前にメニュー開発の自由度について確認しておくことが大切です。
標準メニューのみでは物足りないと感じる場合は、自由度の高いチェーンを選ぶことも一つの選択肢と言えるでしょう。
ブランドイメージの影響

ラーメンフランチャイズに加盟する際は、チェーン全体のブランドイメージが自店に与える影響を考慮する必要があります。
フランチャイズチェーンでは、加盟店同士が互いのイメージを形成し合う関係にあります。
他店の接客やサービスが悪ければ、チェーン全体の評判を下げる恐れがあるのです。
特に、チェーンの知名度が高いほど、ブランドイメージの影響力は大きくなります。
加盟を検討する際は、本部の経営理念やサービス基準が自身の考えと合致するか確認することが重要です。
また、チェーン全体の評判を確認し、加盟後のリスクを予測しておくことも必要でしょう。
ブランドイメージは、集客力に直結する大切な要素です。
自店の経営方針とチェーンのイメージが合致するかどうか、慎重に見極めることが求められます。
競合避止条項の確認

ラーメンフランチャイズの契約書には、競合避止条項が含まれていることが多いです。
これは、加盟店が契約期間中や契約終了後に、同業他社や類似業種への転業を制限する条項のことです。
例えば、「契約終了後1年間は、半径5km以内でラーメン店を出店してはならない」といった内容が定められているケースがあります。
この条項は、加盟店の独立を制限し、本部の利益を保護するために設けられています。
加盟を検討する際は、競合避止条項の有無と内容を十分に確認し、将来的な事業展開への影響を見極める必要があります。
特に、将来的に複数業態の展開を考えている場合は、競合避止条項が障壁とならないかチェックすることが大切です。
条項の内容次第では、事業の選択肢が狭められる恐れもあるため、慎重な検討が求められるでしょう。
ラーメンフランチャイズ成功のポイント

ラーメンフランチャイズで成功するためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。
まず、優れた人材の採用と徹底した教育が欠かせません。
接客やサービスの質は、スタッフの能力に大きく左右されます。
自店の理念に共感し、高いモチベーションを持つスタッフを採用することが重要です。
また、本部の研修制度を活用し、スタッフのスキルアップを図ることも大切でしょう。
次に、効果的な集客活動にも注力する必要があります。
ラーメンフランチャイズでは、本部の広告宣伝に加えて、自店での集客努力が求められます。
SNSを活用した情報発信や、地域のイベントへの参加など、自店の魅力を積極的にアピールしていくことが重要です。
加えて、適切な売上目標の設定と管理も欠かせません。
目標達成に向けて、日々の売上データを分析し、改善策を講じていく必要があります。
食材の仕入れや労務管理など、経費のコントロールにも注意を払いましょう。
最後に、成功するオーナーに共通する特徴として、高い経営意識とリーダーシップが挙げられます。
フランチャイズオーナーには、店舗運営だけでなく、スタッフのマネジメントや数字の管理など、経営者としての能力が求められます。
自己研鑽を怠らず、常に高い意識を持って店舗運営に臨むことが、成功への近道と言えるでしょう。
人材採用と研修体制

ラーメンフランチャイズで成功するためには、優秀な人材の確保と育成が欠かせません。
店舗運営の要であるスタッフの質が、顧客満足度やリピート率に直結するからです。
まず、採用に当たっては、フランチャイズの理念に共感し、高いモチベーションを持つ人材を見極めることが重要です。
単なる飲食店経験者ではなく、接客やサービスへの情熱を持つ人材を優先的に採用することをおすすめします。
また、アルバイトスタッフであっても、将来の幹部候補として育成できる人材を見抜く眼を持つことが求められます。
次に、採用後の教育体制づくりも重要なポイントです。
フランチャイズ本部が提供する研修制度を最大限に活用し、スタッフのスキルアップを図ることが大切です。
接客マナーやオペレーション、衛生管理など、本部の定める基準を確実に身につけさせることが求められます。
加えて、店舗独自の研修プログラムを用意することも効果的でしょう。
店舗の特性に合わせた接客ロールプレイングや、メニューの知識を深めるテストなどを定期的に実施し、スタッフの成長を促すことが重要です。
人材の採用と育成に注力することで、店舗の人的基盤を強化し、安定した運営を実現することができるでしょう。
効果的な集客活動

ラーメンフランチャイズの加盟店は、本部の集客支援を受けられる一方で、自店での集客活動にも注力する必要があります。
地域密着型の営業活動を行うことで、店舗の認知度を高め、リピーターを獲得することが可能となります。
まず、SNSを活用した情報発信が効果的です。
自店のこだわりや特徴を伝える投稿を定期的に行い、フォロワーとのエンゲージメントを高めていくことが重要です。
魅力的な写真や動画を活用し、視覚的にアピールすることも大切でしょう。
また、地域のイベントへの参加も有効な集客策の一つです。
お祭りやスポーツ大会など、地域の一大イベントに出店することで、多くの潜在客にアプローチすることができます。
その際、来場者にインパクトを与えるようなブース装飾や、特別メニューの提供などを工夫することが重要です。
加えて、地元メディアへの露出も欠かせません。
地方新聞社やケーブルテレビ局などに、自店の取り組みや特徴をプレスリリースすることで、メディア露出を獲得することができるでしょう。
口コミの広がりを狙って、ブロガーやインフルエンサーを招待するのも一つの手です。
効果的な集客活動を継続的に行うことで、地域に根付いた店舗づくりを進めることができます。
本部の支援と自店の努力を組み合わせ、足元からファンを増やしていくことが重要だと言えるでしょう。
売上目標の設定と管理

ラーメンフランチャイズ加盟店の経営において、適切な売上目標の設定と管理は欠かせません。
目標達成に向けて、日々の営業活動を最適化していくことが求められます。
まず、売上目標の設定に当たっては、過去の実績や市場動向を踏まえ、現実的な数値を設定することが重要です。
本部の担当者と相談しながら、店舗の立地や規模に見合った目標を設定しましょう。
目標が高すぎると、スタッフのモチベーションを下げてしまう恐れがあります。
一方、低すぎる目標では、経営の効率化が進まない可能性があります。
適切なレベルの目標を設定することが、店舗運営の鍵となります。
目標を設定したら、日々の売上動向を注意深く管理していくことが求められます。
POSシステムなどを活用し、時間帯別の売上推移や客単価、リピート率などを常にチェックしましょう。
売上が目標を下回る場合は、原因を分析し、速やかに対策を講じることが重要です。
スタッフの配置見直しやメニューの改善、販促活動の強化など、柔軟に対応策を打つことが求められます。
売上管理と同時に、食材の仕入れや労務管理などのコスト管理にも注力する必要があります。
売上とコストのバランスを取りながら、利益率の向上を目指すことが重要だと言えるでしょう。
成功するオーナーの特徴

ラーメンフランチャイズで成功するオーナーには、いくつかの共通する特徴が見られます。
これらの特徴を理解し、自己研鑽に努めることが、経営力の向上につながると言えるでしょう。
まず、成功するオーナーは、高い経営意識とリーダーシップを持っています。
店舗運営のあらゆる局面で、経営者としての判断力と決断力を発揮することが求められます。
スタッフの採用や教育、売上管理、コスト削減など、店舗運営に関わる全ての意思決定において、オーナーの手腕が問われるのです。
また、目標達成に向けて、スタッフをまとめ、モチベーションを高めることも重要な役割だと言えます。
加えて、成功するオーナーは、顧客志向が高いという特徴があります。
常に顧客の視点に立ち、ニーズや満足度を考え抜くことが求められます。
味や接客、清潔さなど、あらゆる面で顧客の期待を上回るサービスを提供することが重要です。
顧客の声に真摯に耳を傾け、店舗運営に活かしていく姿勢が欠かせません。
さらに、成功するオーナーは、数字に強い傾向があります。
売上や利益、コストなどの数値を常に意識し、分析することが求められます。
数字を読み解き、課題を発見し、改善策を打つことが重要だと言えるでしょう。
POSシステムやデータ分析ツールを活用し、経営判断の材料としていくことが大切です。
成功するオーナーに共通するこれらの特徴を身につけるには、日々の実践と学習が欠かせません。
フランチャイズ本部の支援を最大限に活用しながら、自己研鑽を続けることが、成功への近道と言えるでしょう。
ラーメンフランチャイズの事例紹介

社内独立制度が整った事例
ラーメンフランチャイズの中には、社内独立制度を整えることで、優秀な人材の確保と店舗運営の安定化を図っている事例があります。
代表的なのが、「らあめん花月嵐」を運営するカフェレオ株式会社です。
同社では、本部社員が一定期間の研修を経て、フランチャイズオーナーとして独立できる制度を設けています。
本部での勤務経験を通じて、店舗運営のノウハウを習得できるため、独立後も安定した経営が可能となります。
また、独立後も本部との連携が密接に保たれるため、問題発生時のサポートを受けやすいというメリットもあります。
社内独立制度は、オーナーの質を担保しつつ、本部と加盟店の強固な信頼関係を構築する上で効果的だと言えるでしょう。
全国展開している大手チェーン
国内のラーメンフランチャイズの中には、全国規模で店舗網を展開している大手チェーンも存在します。
その代表格が、「幸楽苑」や「来来亭」などです。
幸楽苑は、福島県郡山市に本社を置く老舗チェーンで、全国に400店舗以上を展開しています。
看板メニューである「中華そば」は、豚骨スープをベースにした醤油味で、リーズナブルな価格設定が特徴です。
同社は、店舗数の拡大だけでなく、海外進出にも積極的で、中国や香港、シンガポールなどにも出店しています。
一方、来来亭は、愛知県名古屋市に本社を置く、全国展開型のチェーンです。
豚骨醤油ラーメンを看板メニューとし、全国に300店舗以上を展開しています。
フードコートタイプの店舗や、ゴルフ場併設型の店舗など、多様な業態を展開することで、幅広い客層の獲得を目指しています。
これらの大手チェーンは、ブランド力と店舗網の広さを武器に、安定的な集客と売上を確保しています。
加盟オーナーにとっては、全国区のブランドに乗れるメリットが大きいと言えるでしょう。
多様な店舗形態を展開する事例
ラーメンフランチャイズの中には、画一的な店舗展開ではなく、多様な店舗形態を取り入れることで、差別化を図っている事例もあります。
例えば、「麺場 田所商店」は、埼玉県春日部市に本社を置く、関東地方を中心に展開するチェーンです。
同社では、ロードサイド型の店舗だけでなく、ショッピングモールのフードコートや、駅ナカ・駅チカの小型店舗など、様々な業態を展開しています。
多様な立地や店舗形態を組み合わせることで、幅広い顧客層の取り込みを実現しているのです。
また、「Japanese Soba Noodles 蔦」は、東京都内を中心に展開する、つけ麺専門のチェーンです。
同社では、店舗ごとに異なるこだわりのつけ麺を提供することで、画一的なチェーン店とは一線を画しています。
各店舗のオーナーが独自のアイデアを盛り込んだ、個性豊かなメニューが特徴です。
多様な店舗形態を取り入れることで、ラーメンフランチャイズは、競合との差別化を図りつつ、多様な顧客ニーズに応えることが可能となります。
加盟オーナーにとっても、自店の特性に合わせた店舗展開ができるメリットは大きいと言えるでしょう。
セントラルキッチンによるサポート体制
ラーメンフランチャイズの中には、セントラルキッチンを設けることで、加盟店の調理負担を軽減し、品質の均一化を図っている事例があります。
代表的なのが、「麺屋はなび」です。
同社では、スープや麺、具材などの主要食材を、本部のセントラルキッチンで一括して製造しています。
これにより、各店舗の調理工程を最小限に抑えつつ、どの店舗でも同じ品質の商品を提供することが可能となっています。
また、セントラルキッチンの活用は、食材の大量仕入れによるコストダウンにも寄与しています。
仕入れや調理にかかる手間を削減できるため、オーナーは接客や店舗運営に集中することができます。
セントラルキッチン方式は、品質管理と経営効率化の両立を可能にする、ラーメンフランチャイズならではの取り組みだと言えるでしょう。
ステルスフランチャイズの展開例
一般的なフランチャイズとは異なる形態として、ステルスフランチャイズを展開しているチェーンも存在します。
ステルスフランチャイズとは、加盟店が独自の店名や外観を持ちながら、本部のサポートを受けられる仕組みのことです。
その代表例が、「AFURI」や「じぃえんとるまん」などを運営する、株式会社 WDIです。
同社では、加盟店が独自のコンセプトやデザインを打ち出すことを認めつつ、食材の供給や運営ノウハウの提供を行っています。
各店舗が個性を発揮しながらも、本部のサポートを受けられるため、独立開業のリスクを抑えることができます。
また、ステルスフランチャイズでは、のれん分けの形態を取ることも多いです。
本部の直営店で修業を積んだ店長が、独立開業する際に本部のサポートを受けられる仕組みです。
独立に必要な資金や、運営ノウハウを習得できるため、開業後の安定した経営が期待できます。
ステルスフランチャイズは、一般的なフランチャイズの枠にとらわれない、柔軟な店舗展開を可能にする仕組みだと言えるでしょう。
個性的な店作りを目指すオーナーにとって、魅力的な選択肢の一つとなっています。
ラーメンフランチャイズを始めるなら「油そば歌志軒」がおすすめ!

ラーメンフランチャイズを始めるなら、「油そば歌志軒」がおすすめです。
「歌志軒」は、麺を極めたスープのないラーメン「油そば」の専門店として、2010年に名古屋で1号店をオープンしました。
現在では50店舗以上を展開し、独自のタレや調味料の大量生産によるコストカットと、オペレーションのシンプル化で高い利益率を実現しています。
「歌志軒」の油そばは、他のブランドと差別化を図るオンリーワンの商品力が魅力です。
吟味された原料と秘伝の製法で生まれたこだわりの麺、麺の旨みを引き立てる魔法のタレ、アッサリとしてクドくなくコクを醸し出す調合油が、素朴でありながら奥深い味を生み出しています。
また、常時10種類以上あるトッピングや期間限定メニューで、お客様参加型の「楽しみ」を創出しながらブランドを成長させていく点も特徴の一つです。
そして見逃せないのが、麺業態の常識を覆す女性からの圧倒的な支持率の高さ。
トッピングによるカスタマイズの楽しさとヘルシーさが、SNSでの支持や検索率の高さにつながっています。
「歌志軒」では、独立開業に向けて2つのコースを用意しています。
【独立開業の選べる2コース】
=フランチャイズコース=
法人の方、飲食店業界経験者の方、充分な資金を準備できる方におすすめ
=のれん分けコース=
個人の方、飲食店業界経験者の方、今から資金を貯める予定の方におすすめ
フランチャイズコースの魅力
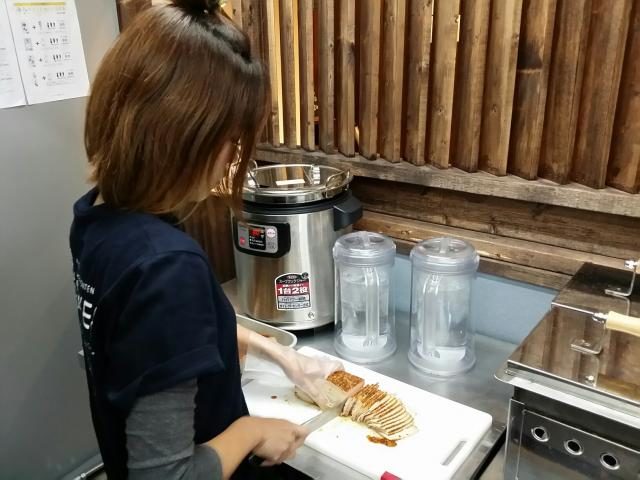
フランチャイズコースでは、店舗運営の基礎をマスターできる充実した研修制度を用意しています。
実際の店舗や研修施設で、接客サービスや調理など実地で学び、必要な知識や技術を身につけることができます。
教育の専門スタッフが丁寧に指導するので、フランチャイズオーナー未経験の方でも安心です。
また、一般的なラーメン店の初期費用が約2,300万円なのに対し、「歌志軒」では800万円から開業可能。
スープ釜が無いので厨房機器も少なく、小さな物件でも対応可能なパッケージとなっています。
半年間の平均月間売上は550万円。
店舗状況にもよりますが、充分な利益を見込むことができるでしょう。
のれん分けコースの特徴

一方ののれん分けコースは、「歌志軒」オリジナルの独立支援システム「実 MINORI」を活用した自己資金0円での開業が可能です。
まず社員として入社し、給料をもらいながら店長経験を積んだ上で独立するので、様々な不安要素を取り除きながらオーナー店長としてのスキルを身につけていけます。
キッチンスタッフからスタートし、副店長、店長を経て独立オーナーとなるまでの道のりを、既存店長が丁寧に指導しながらサポート。
着実なステップアップが可能な仕組みとなっています。
オーナーインタビューから見える魅力

実際にフランチャイズオーナーとして活躍されている方々のインタビューからも、「歌志軒」の魅力が伝わってきます。
【オーナーインタビューから見える魅力】
– 美味しい油そばを地元に広めたいという思いからの開業
– 商品の美味しさ、手軽さ、アレンジの楽しさが決め手
– 充実した研修と運営サポートで未経験者でも安心して開業できる
– 詳細なマニュアルとスタッフ育成システムで多店舗展開もしやすい
– 油そばの魅力を一人でも多くのお客様に伝えたいという情熱
オーナーの皆さんの声からは、「歌志軒」の商品力と充実したサポート体制への信頼、そして 油そばの魅力を広めたいという熱い思いが感じられます。
ラーメンフランチャイズへの参入をお考えの方は、ぜひ「油そば歌志軒」に注目してみてはいかがでしょうか。
きっと、新たなビジネスチャンスと可能性が見えてくるはずです。
まとめ

ラーメンフランチャイズは、独立開業の障壁を下げつつ、安定した経営を可能にする仕組みとして注目を集めています。
本部の強力なブランド力や、運営ノウハウのサポートを受けられることが、大きなメリットだと言えるでしょう。
一方で、ロイヤリティの負担や、メニューの自由度など、フランチャイズ特有の制約も存在します。
加盟を検討する際は、各チェーンの特徴を十分に吟味し、自身の目指す店作りとの整合性を確認することが重要です。
また、成功事例に見られるように、独自の強みを持つチェーンも数多く存在します。
社内独立制度や多様な店舗形態、セントラルキッチン方式など、各チェーンの特色を理解した上で、最適な選択を行うことが求められるでしょう。
ラーメンフランチャイズは、飲食業界への参入障壁が高まる中で、有望な選択肢の一つとなっています。
本部の支援を最大限に活用しつつ、オーナー自身の創意工夫を発揮することで、持続的な成長を実現することができるはずです。
自身の理想とするラーメン店の実現に向けて、フランチャイズという選択肢を検討してみてはいかがでしょうか。
チャレンジする価値は十分にあると言えます。

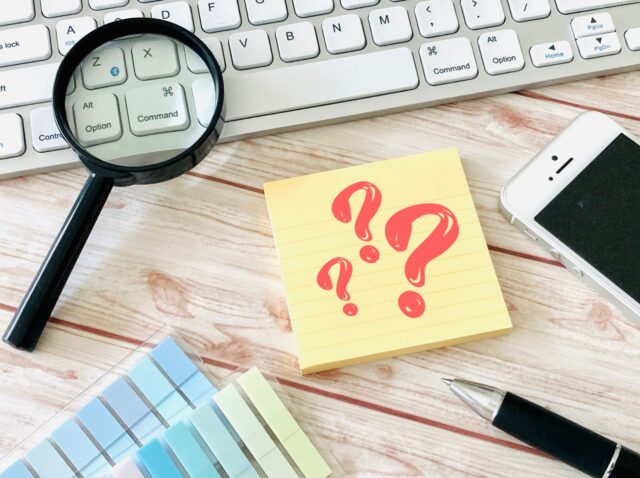


 KAJIKEN
KAJIKEN